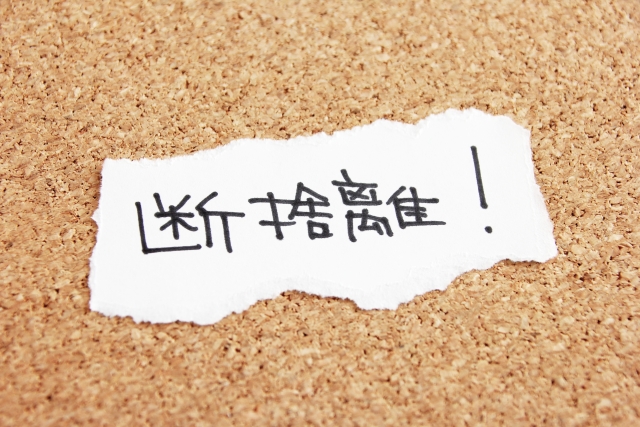断捨離(だんしゃり)を知っていますか?
意味までは分からなくても、どこかで見たことや聞いたことくらいはあるのではないでしょうか。
本屋の生活関連のコーナーにいってみると、片付けや整理整頓術などの本と並んで断捨離と書かれている本が並んでいます。
でも、断捨離は、世に出てから10年ほどしか経っていない新しい言葉(考え方)だとご存じだったでしょうか。
そんな新しい言葉である断捨離が、なぜこんなに認知され市民権を得たのか、その謎を「みんなの5S」流に考えてみました。
Contents
断捨離とは
断捨離とは、2009年末に出版された、やましたひでこさんの著書(新・片づけ術「断捨離」)の中で紹介された、不要な物を減らし、生活に調和をもたらそうとする考え方です。
もともと断捨離は、やましたさんが考案し商標登録された独自の言葉です。それが断捨離を紹介する本を出版後、2010年の流行語大賞にノミネートされるなど、一般でも広く認知されました。
断捨離はとても奥の深い考え方ですが、簡単に言うと「①不要なモノが入ってくるのを断ち、②要らないモノを捨てて、③モノへの執着から離れる」ということです。
なぜ断捨離が日本で流行したのか
流行語大賞にノミネートされ、やましたひでこさんをはじめ、多くの人が断捨離の考え方や実践方法などを著わした書籍やネット記事が書かれています。
なぜ日本で、これだけ断捨離が流行したのでしょう。
それは、行き過ぎたもったいない精神によって、モノを捨てられないという、多くの日本人が抱える悩みにマッチしたからです。
日本のもったいない精神
日本は、平野の少ない島国で、昔から資源に乏しく農作物の作付面積が小さい国でした。なので、限られた食べ物や材料を、無駄に使うことなく、いかに効率よく消費するか、また道具などを手入れして、いかに長く使うかが得意な国になりました。
地域にもよりますが、学校教育でも、給食の食べ残しや水の無駄遣いなどをしないように、勉強道具や部活の用具なども丁寧に使うように指導しています。
こういった積み重ねから生まれたのがもったいない精神です。
このもったいない精神は、大量生産・大量消費でゴミ問題が深刻化した近年、世界的に注目され、賞賛された考え方です。実際、海外から日本に来た方で、普段の何気ない行動にもったいない精神が根付いていることに感動した、といった例は多く、日本の誇るべきものの1つといえるでしょう。
もったいなくて、モノを捨てられない

でも、行き過ぎたもったいない精神は、「もったいなくて、モノが捨てられない」といった問題をつくってしましました。
異臭を放ち、虫がわくゴミ屋敷は近くに住む人の迷惑となり、テレビや週刊誌でも取り上げられるほどの社会問題となりました。
そこまでいかなくても、使わない食器が戸棚に眠っていたり、何年も着ていない服がクローゼットにかかったままだったり、苦手な食べ物をプレゼントされて冷蔵庫で賞味期限を迎える・・・・・・といったことは、普通の家庭でもよくあることです。
そんな捨てられない日本人の心を軽くしたのが「断捨離」でした。
断捨離でモノへの執着から離れる
断捨離は、「そのモノ自体が使えるかではなく、自分が使うかどうか」を基準に、残すか捨てるかを判断します。
捨てられない人は、まだ使えるのにもったいないから捨てられないわけです。ただ、その捨てる捨てないの判断は、モノを中心に考えていますよね。断捨離の場合は、自分にフォーカスしてます。
あなたはどんな人生を過ごしたいですか?
その人生の中で、今、手に取っているモノは本当に必要ですか?
必要なら、使いやすいように片付けましょう。
不要なら、買わないようにしましょう。捨てましょう。
モノへの執着から離れて、軽やかに生き生きとした生活を手に入れましょう。
断捨離は新しいライフスタイルの提案だったのです。
「使えるのに捨てるのはもったいない」という教育を受けてきたけど、自分の生き方、ライフスタイルを中心に、モノを選んでもいい、捨ててもいいんだっていう考えに共感した人が多かったのが、ここまで断捨離が流行った理由だと私は考えています。
断捨離と5S
最後に、断捨離と5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の関係についてです。
断捨離は、5Sを実践する上でとても大切な考え方です。これは、家庭の5Sはもちろん、仕事で使う場合の5Sも同じです。
前述の通り、断捨離は自分の生き方を中心としてモノの価値を判断する考え方です。
5Sの【整理】は、必要なモノと不要なモノを選別して、不要なモノを捨てることですが、その判断基準に、断捨離の考え方を取り入れると上手くいきます。
家庭の5Sと断捨離

家庭の5Sを行う場合、それぞれのご家庭の価値観・生活観を基準に断捨離を行うと良いでしょう。普通の断捨離の考え方ですね。
ひとり暮らしの場合は簡単で、自分の生き方や価値観で断捨離を行い、5Sを実行すればOKです。
パートナーがいたり、同居人がいる場合は、ちょっと面倒ですが、一度みんなでどんな部屋にしたいかを共有すると良いでしょう。
ただ単に、モノが多すぎて片付かないから捨てるというのは少し乱暴です。ひょっとしたらその人にとっては理屈ではなく大切なモノかもしれません。といっても、モノが多すぎるのは問題なので、そこを解決するために、家族みんなの価値観の共有を行います。
といっても難しく考えずに、片付けたい、捨てたい理由と捨てて欲しくない理由について話し合うだけで良いです。じっくり長時間話しても良いですが、無理なら少しずつでも意識して会話に乗せるだけでもいいでしょう。
それこそ、断捨離の本などを利用して、できるだけ写真やイラストなど具体的に想像できる材料を持って話すと効果的ですよ。
職場の5Sと断捨離
職場での断捨離は、企業文化や社風などもありますが、社員一人ひとりの価値観というより、会社全体の価値観が明確なので進めやすいです。
基本的には、ムダなモノは買わない。使えない(故障等)モノは使えるようにするか他に回わすか捨てる。不必要なモノを買わないような仕組み(購入伺いや購入リスト)などを使う。などなど、経費削減や生産性向上、スペースの有効活用などを基本に置くと良いでしょう。
逆に、断捨離がすんなりいかないようであれば、断捨離を行うことで仕事自体の目的や価値観がはっきりとします。効率が上がり、業績がアップすることもあります。
なぜ必要か。もし必要なら使いやすいように整頓する。
なぜ不要なのか。もし不要なら整理する。
この「なぜ」という価値観の共有が、職場に一体感をもたらし、ムリムダの排除に繋がります。結果、職場の5Sを進める上でも、やらされている感はなくなり、モチベーションもアップします。
まとめ-断捨離は単に捨てることではない-
断捨離は、単に捨てるための技術ではありません。
こんな生き方だと、しがらみもなく生き生きと生活できるよね!っていう新しい価値観、ライフスタイルの提案です。
なので、家庭でも職場でも、モノの優劣やもったいないのでとりあえず持っておこうという考えではなく、断捨離を活用し、何が大切で何が大切ではないのかという価値観を共有して、より良い生活環境、職場環境に整えて下さいね。